| FinalCutPro Unofficial的には、まずキャプチャーのレビューから入ります(笑)。というのは、ここを見るとFCEの性格が見えてくるからです。
キャプチャーは非常にシンプルで、ご覧の通り1つのタブ構成です。
これはキャプチャーできるのがDV25(25MbpsのいわゆるフツーのDV-NTSC/PAL)のみなので細かい設定そのものが無いことと、ターゲットがコンシューマーや部署内の内製、iMovie卒業ユーザーといった層だからでしょう。ここでやるのはキャプチャーで、32kか48kか、4:3か16:9か、といった設定は簡易セットアップで選ぶ、というように分けられています。
取り込みモードは「クリップ」「今すぐ」に加えて、「ログ」 がない代わりに「プロジェクト」というモードがあります。 そして、デバイスコントロールとタイムコードのIN/OUTがありますね。
つまり、見た目はFCPですが、機能としてはiMovieを拡張したようなもので、IN/OUTとクリップ名を指定したカット取り込みが行えますが、取込む前にクリップをログしておくバッチ取り込みはできません。
また、FCEでの作業を通してユーザーがタイムコードを意識するのはキャプチャーだけで、基本的には編集中はタイムコードは気にしなくていいようになっています。
では時間軸に沿ったビデオをどのように編集するのかといえば、焦ることはありません。
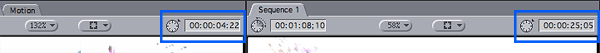
気にしなくていい、というかタイムコードが扱えない、というのは、なんのことはない、どのクリップも00:00:00:00から始まる「タイマー(CTL)方式」なんですね。テープに記録された「絶対番地」を拠り所とすることができないだけで、フレーム単位で編集することはもちろん可能です。シーケンスも00:00:00:00スタートで、変更することはできません。
ですから、iMovieを卒業したいけどテープのタイムコードなんかは気にしない、といった向きにはクリップもシーケンスもデュレーション(継続時間)ベースなので解りやすいのではないでしょうか。
これを踏まえて、キャプチャーの「プロジェクト」というのは何かというと、実はFCEはクリップのタイムコードをしっかり覚えてるんです。しかし、編集中は表に出てきません。じゃあ結局iMovieと変わらんではないか、というとそこはFCPの血を引く(というか機能限定の)FCE。一通り編集が終わってクリップを削除したり、間違って消してしまったとしても、タイムコードはしっかり覚えているので、DVテープからDV接続でキャプチャーしている限りはこの「プロジェクト」キャプチャーボタンでバッチキャプチャーによる復元を行ってくれるというわけです。
そのために、 ここはFCP同様クリップ名の他にテープ名も決めてあげることができるようになっています。
|
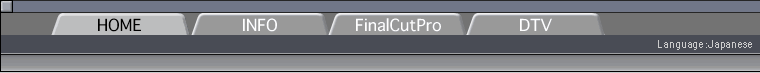
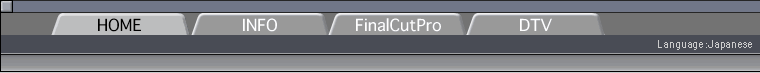
![]()